旅行先や出張先など、どこでもライブ配信や動画編集ができるゲーミング&クリエイター向けノートパソコンをご紹介します!高性能な第13世代Intel CPUとAV1エンコードが可能なGPU RTX4060搭載し、ゲーマーやクリエイターにも最適な格安価格で販売されている1台となっております。
- Nvidia GeForce RTX4060搭載PCのメリット
- Lenovo LOQ 15IRH8 82XV006JJPのサイズと重量
- フルHD15.6インチのノングレアIPS液晶ディスプレイの品質は?
- キーボードは暗い場所でも操作が可能なバックライト付き
- 裏面は巨大な吸気口になっているので、冷却対策は必要
- 高速転送に対応をした豊富な入出力端子
- Lenovo LOQ 15IRH8 82XV006JJPの性能
- RTX3060搭載デスクトップとLenovo LOQ 15IRH8 82XV006JJPのグラフィック性能
- 内蔵バッテリーとACアダプターの消費電力
- Wi-Fiの受信電波強度はTP-Linkのハイゲインアンテナと同等
- 電源管理やGPUのオーバークロックも可能なソフトウェアが便利
- Lenovo LOQ 15IRH8 82XV006JJPの評価
Nvidia GeForce RTX4060搭載PCのメリット
Nvidia GeForce RTX4050からRTX4090までのGPUを使用するメリットは、処理が重い3Dゲームのプレイや映像編集が出来るようになるだけではなく、次世代ビデオコーデックのAV1が使用出来る事にあります。
動画のエンコードのみであれば、H.264やH.265(HEVC)よりもファイルサイズを小さく出来る事しかメリットがありませんが、AV1を使用出来る事で恩恵を受けるのが、低速回線を使用した動画のライブ配信です。
光回線を使用したライブ配信であれば、よっぽど品質が悪い回線じゃない限りは、特に大きな問題になりませんが、不安定で回線速度が遅いモバイル回線を使用したライブ配信では、フレームドロップの多発でまともに通信を継続できない事も起こります。
低速不安定になっている通信回線に合わせて、ビットレートや解像度を下げて配信を行うという手段もありますが、不鮮明な映像となってしまったり、ブロックノイズの発生が抑えられない事態にもなります。
低いビットレートでも映像の品質を保ったまま配信をするためには、圧縮効率が高い動画コーデックのAV1が使用出来るRTX40系グラフィックボードが必要になってくるわけです。
ネットフリックスも採用する次世代動画コーデックAV1とは?
様々な機器で広く普及したH.264 / MPEG-4 AVCの後継規格として、圧縮効率に優れて8K解像度までサポートしているH.265 / MPEG-H HEVCが注目されるようになりました。
HEVCは2013年にITU-T(国際電気通信連合)によって国際標準規格として承認され、従来のH.264よりも圧縮効率に優れたビデオコーデックとして、動画撮影機能付きカメラなどに普及していました。
しかし、H.264ほど普及しなかった背景には、利用するにあたって特許使用料の支払い義務が生じてしまう事にあり、アップルのiOSで対応をするようになったのも、2017年の秋頃だったのです。
そこで登場したのが、AOMedia(Alliance for Open Media)が開発した、オープンかつロイヤリティフリーな動画圧縮コーデックAV1(AOMedia Video 1)です。
AOMediaは、Intel・Microsoft・Netflixなどの名立たる企業が共同で設立した非営利団体で、VP9や高額な特許使用料がかかるHEVC/H.265の置き換えを目指してAV1を開発しました。
AV1は、主にGoogleのVP9にDaalaとThor、VP10の技術を組み込んで開発し、HEVC比で30~43%ほどビットレートを削減できるのです。
AV1の対抗としてVVC/H.266の開発も進められていますが、既にNetflixやYouTubeなどがAV1を使用したストリーミングを開始しているため、画質を維持したまま低いビットレートでデコードが可能なAV1は、ストリーミング再生に強いビデオコーデックとして注目されているのです。
Nvidia GeForce RTX4050よりRTX4060の方がオススメ?
圧縮効率が高いAV1を使用したライブ配信をするのみであれば、RTX40シリーズの中でもエントリーモデルとして位置付けられているRTX4050でも可能です。
ライブ配信用途のみに絞ったゲーミングノートPC選びであれば、それでも別に良いのかもしれませんが、4K映像のエディットや中画質の3Dゲームのプレイもするのであれば、もう少し内部ハード面のスペックが高くても良いぐらいです。
筆者も購入時に迷いましたが、ライブ配信では大丈夫でも、処理が重いエフェクトを使用した動画編集はVRAM容量がネックになっているので、容量が大きいRTX4060を選んだのは正解だと思っています。
ポストプロダクションソフトウェアのBlackmagic Design DaVinci Resolveを使用するのであれば、RTX4050に搭載されている6GB VRAMは軽い編集でもギリギリの容量になるので、ノイズリダクションなどの重いエフェクトを使用してもギリギリ動かす事が出来る、VRAM容量8GB以上を搭載しているRTX4060以上の方がオススメです。
Lenovo LOQ 15IRH8 82XV006JJPのサイズと重量
Lenovo(レノボ) LOQ 15IRH8のサイズは幅359.6mm、奥行きは264.8mm高さは25.2mmで、15.6インチディスプレイとGPUを搭載したノートブックPCとしては平均的なサイズに抑えられています。
色はチタンカラーに似たストームグレー1色が設定されており、閉じた状態で文字が光るようなライティング機能はありません。
また、本体の重量は2.4kgもあるので、グラボ非搭載の標準的なビジネスノートPCと比較すると、ずっしりとした印象は受けてしまいます。
フルHD15.6インチのノングレアIPS液晶ディスプレイの品質は?
フルHD 144Hzで表示するディスプレイは中国のBOEテクノロジー製
Lenovo LOQ 15IRH8 82XV006JJPに内蔵しているディスプレイは、ノートPCとしては標準的な色域となるNTSC45%のノングレアIPS液晶ディスプレイを採用しており、解像度はフルHD(1920×1080)、リフレッシュレートは144Hzほどの性能になります。(a-Si TFT-LCD説あり)
ディスプレイの品番はNE156FHM-NX3で認識し、どうやら中国の大手ディスプレイメーカーであるBOEテクノロジーグループが製造した製品である事が判明。
2013年よりシャープから技術供与を受けてIGZO液晶ディスプレイを製造していたCECパンダの成都工場と南京工場を2020年に買収して、IGZO技術を取得した後に大型OLEDパネルを量産しているメーカーなのだそうです。
sRGBやAdobeRGB以上の写真編集や、Rec.709以上の動画編集など、徹底的に色にこだわりたい方には向かない色域となりますが、実際にキャリブレーションソフトウェアを使用して、対応をしているカラースペースやルミナンスを測定してみました。
ホワイトポイントと最大輝度の実測値は?
製品仕様書のホワイトレベルは381cd/㎡になっていますが、実際の測定結果は363.64cd/㎡が最大の明るさとなり、ホワイトポイントは若干グリーンが落ちている様子も見受けられるものの、ほぼ6500Kに近い白を表示する事が出来ています。
20cd/㎡の誤差であれば高品質なカラーマネジメントディスプレイでも良くみられる数値なので、非常に明るく白色点の大きな崩れがほとんど無い品質には収まっております。
色域はsRGB比54%・写真や映像編集は外部モニター必須
カタログ上ではNTSC比45%の色域となっておりますが、sRGBでの測定結果でもさほど広さを感じられない色域に収まっています。
実際にBOE NE156FHM-NX3のスペックシートを見てみるとsRGB比で54%の色域になっているのが正式なデータらしいので、ディスプレイの表示性能を落として値段に反映させたロープライスゲーミングノートパソコンという事になります。
Calibration curvesも、低価格帯ディスプレイでよく見かける曲線になっているので、黒が沈みすぎている点も含めて内蔵ディスプレイ単体での写真のRAW現像や動画のカラーグレーディングには向かなさそうです。
コントラスト比は実測1300:1、海外仕様はsRGB100%の可能性
その代わりにコントラスト比は実測1300:1(スペックシートは1000:1)ぐらいあったので、色域は低いけど見れないというほど薄っぺらな映像にはならない点については割と好印象でした。
海外仕様だとLOQ 15IRH8のWQHD sRGB100%仕様もありますが、ディスプレイの品番がBOE NE156QHM-NY4(5D11D04810)の40pinとなっていたので、認識さえ出来れば海外仕様への交換も可能なのかもしれません。
Amazonでも同型品番のディスプレイが販売されていますが、販売価格が$500前後でメーカー名がBOEテクノロジーになっている製品が一つも見つからなかったため、低価格な粗悪互換品である可能性が高い事には注意が必要です。
価格を抑えてGPUとCPUの総合性能に全振りをしたようなラップトップなので、メインPCでLUTやプリセットを予め作れる方や、HWキャリブレーションが可能な広色域ディスプレイを使用をする前提で考えているプロの人でも問題なく使用出来るかと思います。
キーボードは暗い場所でも操作が可能なバックライト付き
キーボードのキーピッチは16mmで、普段使い用や事務作業用PCとしても活用できるサイズと高さに抑えられているようです。
また、Fnを押しながらF1~F12を同時に押すとスピーカーの音量やディスプレイの明るさの調整、その他様々な機能のオンオフをワンタッチで出来るのが個人的に扱いやすいと感じました。
キーボードのイルミネーション機能はゲーミングPCにありがちなカラフルなものではなく、暗い場所での操作もしやすいホワイト一色のバックライト式となっております。
また、バックライトはFnキーとスペースキーの同時押しで消灯から最大の明るさまで3段階で調整が可能。
実際に大曲の花火 秋の章のライブ配信で使用した際にも、光るキーボードがとても便利でした。
キーボードにタッチする時だけ点灯させて、それ以外の時はFnとスペースキーを押すだけで消灯させる事が可能。
ディスプレイもFn+F5とF6で明るさを調整する事が出来るので、調整の仕方次第ではほぼ消灯に近い所まで、パソコン全体の照明を暗くする事ができます。
裏面は巨大な吸気口になっているので、冷却対策は必要
LOQ 15IRH8シリーズの裏側には巨大な吸気口が設けられており、内蔵された2つの空冷ファンと4本のヒートパイプでCPUやGPUなどを強力に冷やします。
ただし、LOQ 15IRH8シリーズは冷却性能が低いせいなのか、高負荷時にはCPUの温度が高温になりやすい傾向があるので、冷却対策をして温度の上昇とファンの回転数を抑える工夫は必要になるかもしれません。
ファン内蔵の冷却パッドのようなものがベストなのかもしれませんが、角度調整式の折り畳み式ノートパソコンスタンドを使うだけでも高い冷却効果が見られました。
CPUの温度はどちらも100度に達して頭打ちにはなっていましたが、FF15ベンチマーク時のGPUの温度に関しては、スタンドの上に乗せて空気の通り道を作った方が7.5℃もGPUの温度が低くなります。
折り畳んでケースに入れて持ち運ぶ事も出来ますし、角度が付いてキーボードの打ち込みもしやすくなっていたので、ラップトップを使うのであれば筆者的にはオススメの商品です。
空冷ファンの音は、ノーマルモードやサイレントモードでほぼ無音に近い状態ですが、高負荷がかかる動画編集やゲームプレイだと耳障りに感じる事が多いです。
パフォーマンスモードに設定をすると、高負荷時に甲高い音を発しながら爆音でファンが回るので、動画のエンコード中にその場を離れるなら気にならないけど、ゲームプレイ中は結構気になるレベルの音量だと思います。
Lenovo VantageかFn+Qでノーマルモードや静音モードに切り替えて負荷がかかっていない状態では、ファンの音は全く聞こえていない無音レベルまで抑えられるので、常時気になるというほどではない点についてはご安心下さい。
高速転送に対応をした豊富な入出力端子
背面はUSB3.2 Gen2とHDMI 2.1端子を装備
背面にはUSB Type-A端子が2つとイーサネット・コネクター(RJ-45)1つ、HDMIコネクターと電源ポートを装備しています。
背面のUSB端子は、3.2 Gen2 type-Aを2ポート搭載し、最大10Gbbsの最大転送速度で、ファイルサイズの大きなビデオデータなどもスムーズに読み書きをする事ができます。
HDMI端子は最大8K/60Hzの伝送も可能なウルトラハイスピード(HDMI 2.1)対応のデジタル映像出力ポートなので、HDR10やHLGなどのHDR映像を外部ディスプレイに出力をする事も可能です。
また、背面標準ポートの両サイドには、内蔵ハードウェアの冷却に使用した空気を排出するための大型排気口が2つ設けられています。
左側面はUSB Type-Cポートとヘッドフォン/マイクコンボジャックを装備
左側面には、データ転送、Power Delivery 140W、DisplayPort™ 1.4 をサポートするUSB-C 3.2 Gen 2端子と、3.5mmのヘッドフォン/マイクコンボジャックを1つ装備しています。
ただし、映像出力はDisplayPort Alt ModeやThunderbolt 3以降には対応しておらず、USB Type-C to Display Port 1.4に変換をするケーブルが必要になってしまう仕様が少々残念。
右側面はUSB 3.2 Gen 1とカメラのオンオフスイッチを装備
右側には最大転送速度が5Gb/sのUSB 3.2 Gen 1端子と、フルHD記録の内蔵カメラをオンオフを切り替えられるスイッチが備えられています。
82XV006JJPの中では低速のUSB規格となっているので、高速な転送速度を必要としない機器を接続したり付属の有線マウスを使う時に使用します。
USB 3.2 Gen2ポートはType-AとType-C共に超高速
左側USB 3.2 Gen2 Type-Cと背面USB 3.2 Gen2 Type-Aの両方にCinema SSDを接続すると、シーケンシャルリードで1060MB/s前後、シーケンシャルライトで1000MB/sの速度が出ました。
このSSDが頭打ちになる速度なので、USB 3.2 Gen2の最大転送速度に近いスピードが出ている事が分かります。
USB3.2 Gen1 Type-A端子でも、シーケンシャルリードで458MB/s、シーケンシャルライトで455MB/sの転送速度が出たので、速度を抑えても支障が無い機器や意図的に速度を抑えたい機器を右側USB Type-A端子を使うのが良さそう。
通常は、付属する有線ゲーミングマウスを接続するために使用をするポートです。
Lenovo LOQ 15IRH8 82XV006JJPの性能
CPUはIntel第13世代Core i7 13620Hを搭載
Lenovo LOQ 15IRH8 82XV006JJPには、Intel第13世代Core i H45WシリーズCPUのCore i7 13620Hを搭載し、Pコアが6コア、Eコアが4コアの合計10コア16スレッドで処理を行う、中位モデルよりも少し下ぐらいに位置付けられているラップトップ向けCPUです。
定格のクロック周波数は 2.40 GHzで、ターボ・ブースト利用時の最大周波数は4.9GHzに達します。
ラップトップ向けCPUの中では比較的消費電力が高い方で、ゲームプレイや動画編集を快適にするために、省電力性能よりもパフォーマンス性能を優先しているモデルとなっています。
Lenovo公式のソフトウェア「Lenovo Vantage」でパフォーマンスモードを管理する事が出来ますが、温度や消費電力の問題があるのか、意図的にターボモードの4.9GHzに抑えていそう。
13世代/14世代インテルCPUの不具合該当リストにCORE i7 13620Hが入っておりませんが、多少は制限を設けているのかもしれません。
多分、価格が安かったのも13世代/14世代インテルCPUで発生した不具合の煽りを受けて売れなかったのが理由だと思いますが、最終的な不具合修正パッチが適用されたBIOSが10月に登場しているので、現在は問題が無いものと考えても良いでしょう。
GPUはAV1エンコードも可能なNvidia 4060を搭載
決算と在庫処分セールだったのもあるかと思いますが、Nvidia RTX4060搭載モデルの中では多分最安価格の13万円でした。
RTX4060の定格クロック周波数は1545MHz-2295 MHz、最大クロック周波数1890MHz-2370MHzで動作し、GDDR6 8GBのビデオメモリー(VRAM)を搭載しています。
CUDAコア数は、RTX3060の3584基(Laptopは3840基)からRTX4060は3072に減らされているため、DaVinci Resolveを使用した6K RAWの4K動画書き出しでは、4~5fpsの書き出し速度の低下は見られます。
しかし、ライブ配信では、HEVCよりも軽量なAV1エンコードに対応しているのは現状でRTX40シリーズGPUのみになっているため、高速で安定した通信回線を確保できないような時にはとても有利になります。
本格的なゲーム用途や動画編集用途で、AV1へのこだわりが無ければ、RTX4060よりもRTX30シリーズの上位モデル、予算があったら40シリーズの上位モデルが入ったゲーミングノートPCの方がサクサク動くかと思われます。
DRAM容量は平均的な16GBなので少し物足りない
Lenovo LOQ 15IRH8 82XV006JJPのDRAM(メインメモリー)の容量は8GB2枚の16GBしかないため、負荷のかかる動画編集では動かない事はないけど少し物足りない容量です。
海外のフォーラムやスペックシートを見てみると、16GBの2枚差しで最大32GBのDDR5 5600MHz(公式には4800か5200)に換装できている事を確認出来ているため、限界を感じたら自己責任で容量を増やしてみるのも良いのかもしれません。
i7 8700とRTX3060を搭載したデスクトップのサブ機として購入をしたつもりだったけど、CPUの性能が高い分、ノイズリダクションのような重い処理をCPUに回すと想像以上にサクサクと書き出してくれています。
内蔵NVMeは512GBだけど、M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 スロットに空きあり
LOQ 15IRH8 82XV006JJPに内蔵されているストレージは、容量512GBのM.2 2242 NVMe SSDです。
シーケンシャルリード3240MB/s、シーケンシャルライトで3179MB/sの高速な転送速度を発揮するNVMeですが、容量が512GB/sなので、外部ストレージを使わないと容量が足りなくなると思います。
純正のNVMeはM.2 2242サイズですが、もう1ヶ所内部にM.2 2280サイズの空きスロットがあるので、そちらにNVMeを増設すれば最大1TB+1TBの合計2TBにまで容量を増やせる仕様になっているらしい。
日本国内向けレノボ公式サイトには多分無いけど、海外のレノボ公式サイトには製品仕様参照(Product Specifications Reference)にストレージやDRAMのテスト済み最大容量が掲載されています。
他の国の仕様では同じCPUとGPUでもNVMeが1TBになっていたり、ディスプレイがsRGB100%のWQHDになっていたりするので、良く言えばアップグレード、悪く言えば魔改造の参考にしてみるのも楽しいかもしれません。
国内サイトに無いのは、保証の都合もあるかもしれないので、もし増設や換装を希望する方は自己責任でお願いします。
RTX3060搭載デスクトップとLenovo LOQ 15IRH8 82XV006JJPのグラフィック性能
DaVinci Resolveの4K HDR書き出し性能
普段はDRAM容量32GBのデスクトップ水冷自作機にi7 8700とRTX3060を搭載したメインPCで、6K RAWのカラーグレーディングと4K HDR映像の書き出しをしています。
今回購入をしたLenovo LOQ 15IRH8 82XV006JJPで同じ編集と書き出しを行うと、3060よりも4fps~5fpsほどの性能低下が見られました。
RTX4060はRTX3060よりもCUDAコア数を500~800基近く減らしているため、GPUとビデオメモリーに負荷がかかるDaVinci Resolveを使用したHEVC Main10 HLGの書き出しでは、少なからず影響はあります。
DRAM容量は最大でも14GBまでしか使われていなかったので、DaVinci Resolveを使う分にはノーマルスペックでも大丈夫そう。
逆にDRAMを大量に消費するAdobe Premiere Proを使用するのは、少々難しいかもしれないです。
13世代のCPUが偉大だったノイズリダクションを使用した書き出し
処理がかなり重いノイズリダクションプラグイン「Neat Video v5」を適用してDaVinci Resolveで書き出しを行うと、i7 8700とRTX3060 12GBを搭載したデスクトップ機と、i7 13620HとRTX4060を搭載したLenovo LOQ 15IRH8では立場が逆転します。
Neat VideoでCPUとGPUの両方を使う設定でノイズを軽減しながら書き出しを行うと、RTX3060を搭載したデスクトップは5~5.5fpsで処理と書き出しを行ってくれます。
RTX3060の専用GPUメモリを使い切って共有GPUメモリを一部使用していますが、ノイズ軽減処理の大部分をGPUが行っていたため、CPUは20%~30%ぐらいしか使われません。
その一方で、RTX4060を搭載した第13世代CPUのLenovo LOQ 15IRH8でノイズ軽減処理を行いながら書き出しを行うと、6fps~6.5fpsで書き出しが出来ておりました。
VRAM容量8GBがボトルネックになっている部分はありますが、Intel CPU5世代分の差が書き出し速度に影響しているので、Lenovo LOQ 15IRH8をサブ機と呼ぶには少々もったいないような気もします。
また、350W近い電力を消費するデスクトップよりも150W~170Wの消費電力で書き出せるLenovo LOQ 15IRH8の方が電気代もかからないので、DaVinci Resolveのプロジェクトを移してノートPCで書き出しをした方がお得なのかもしれません。
今までは、デスクトップPCじゃないと重いエフェクトを使用した動画編集は難しいと思っていましたが、ライブ配信と軽い動画編集さえ出来れば良いと思って購入をした激安ゲーミングノートPCでも出来るという結果になりました。
FFXVベンチマークはRTX4060の方がスコアが高くなる
FFXVベンチマークで4K UHDのスコアを比較すると、RTX3060 12GBは4000前後のスコアで止まってしまいますが、RTX4060は4300ぐらいまでスコアを伸ばしています。
低解像度の画像を高解像度にアップスケールしてフレームレートを伸ばすDLSSを有効にするとさらに差が付いて、RTX3060の5760に対してRTX4060は6522までスコアを伸ばしました。
グラフィック性能まとめ
RTX3060とRTX4060を比較すると、CUDAコア数が多くてVRAM容量が大きいRTX3060は動画編集に強く、GPUとVRAMのクロック周波数が高いRTX4060はゲームでスコアを伸ばす事が分かりました。
元々ライブ配信でのAV1出力と速報版動画の書き出しを視野に入れて購入をしたサブ機として位置づけておりましたが、思っていた以上に性能が高くて、型落ちメイン機にも劣らない性能を発揮してくれるノートパソコンだと思います。
DRAMとVRAM容量がボトルネックになるけど、ノイズリダクション付きの動画書き出しなら4K、カラーグレーディングのみなら6Kの出力まで対応出来ます。
内蔵バッテリーとACアダプターの消費電力
高負荷時は外部からの電力供給は必須
容量60Whの4セルリチウムイオンポリマーバッテリーを搭載し、使用時間(JEITA2.0)は約10.0時間。付属170W ACアダプター接続の急速充電モードを使用すると電源オフ時に約2時間でフル充電が可能です。
内蔵バッテリーのみの運用では、バッテリーの残容量100%から動画編集後の書き出しやゲームプレイをすると、約40分で電源が切れてしまいましたが、省電力モードの常時アイドル状態であれば4時間近くは電源が入っていました。
CPUとGPUを占有するような作業をする時には、ACアダプターの使用は必須なので、電源が無いような場所で使用するような時には、ポータブル電源の使用やAC100Vアクセサリーコンセント付きのハイブリッド車の活用も検討した方が良いでしょう。
また、USB 3.2 Gen2 Type-C端子はPD 140Wの給電に対応をしているため、PD出力付きのモバイルバッテリーがあれば、充電をしながら稼働時間を大幅に伸ばす事は可能です。
一応アイドル時であれば60W程度のモバイルバッテリーでも充電は可能ですが、確実に常時給電が出来そうなPD140Wを出力できるモバイルバッテリーを使用した方が良いでしょう。
サーマルモードごとの消費電力と性能の違い
Lenovo Vantageで静音モード・バランスモード・パフォーマンスモードを切り替えて、各設定の消費電力をアイドル時と高負荷時に測定してみました。
消費電力のモニタリングは、ポータブル電源の出力モニターを使用して確認しております。
アイドル状態では全てのモードで20W前後を消費していたので、負荷がかからない時は極力消費電力を抑えて、バッテリーの駆動時間を伸ばすような制御を行っています。
ベンチマークソフトでCPUに負荷をかけて消費電力が最大になるように設定をすると、静音モード時にパッケージ電力45W、Pコア2800MHz・Eコア2200MHzで動作し、その際の最大消費電力は137Wになりました。
高負荷時の空冷ファンの回転数もかなり低く抑えられていたため、パソコンに向かって作業をしていても回転音がほとんど気にならないレベルになっています。
バランスモードに設定をすると、CPUのパッケージ電力が60Wまで上がり、Pコア3300MHz、Eコア2450MHzで動作、最大消費電力は150Wで頭打ちになっています。
ポータブル電源の出力モニターを見る限りでは、AC出力が150Wぴったりで止まっていたため、消費電力150W以内で出せる最大のパフォーマンスで動作しているのだと思われます。
パフォーマンスモードでは、CPUのパッケージ電力を75Wまで上げて、Pコアの最大で4500MHz、Eコアは最大3200MHzで動作し、最大消費電力は180Wに達しました。
日本国内仕様の170WACアダプターから絞り出せる定格以上の最大出力で動作しているので、常時フルパワーで負荷をかけ続けるのは難しいのかもしれません。
CPUとGPUを使用するベンチマークでも、それぞれのサーマルモードの消費電力を超える事が無かったので、サーマルモードで消費電力の上限を設定して、その中でハードウェアの総合パフォーマンスを自動調整する制御が行われているのだと思われます。
3Dゲームや動画編集などではノーマルモードやパフォーマンスモードを使った方が良いと思いますが、事務作業やネットサーフィン、動画や写真の閲覧では、静音モードを使用しても動作がもっさりとするような事はありません。
なお、USB 3.2 Gen2 Type-C端子から給電をした場合は、静音モードとノーマルモードしか選択が出来ず、内蔵バッテリー駆動モードと同様のパフォーマンスに制限をされます。
Wi-Fiの受信電波強度はTP-Linkのハイゲインアンテナと同等
WiFi Analyzerを使用してLenovo 15IRH8 82XV006JJPの内蔵Wi-Fiと自作デスクトップPCに接続したTp-Link Archer TX50UH、東芝dynabook R73/A内蔵のWi-Fiの電波強度を測定しました。
親機は第二世代StarlinkのWi-Fiルーターで、全て測定条件が同じになるように、それぞれ同じ場所に設置をして測定をしております。
内蔵されているネットワークカードは、残念ながら悪評高いRealtek RTL8852BE。時々不安定になる事もあったため、私の場合は保障期間が過ぎてからインテル製に交換をしています。
dynabook R73/A内蔵Wi-Fiの電波強度
dynabook R73/Aは全ての性能が平均的な、法人向けビジネスモバイルPCとして販売されているモデルです。
Wi-Fiの電波強度も-50dBm程度で推移していました。
Lenovo LOQ 15IRH8 82XV006JJPの電波強度
Lenovo LOQ 15IRH8 82XV006JJPに搭載しているワイヤレスアンテナの電波強度は-40~-43dBmで推移していたので、一般的なビジネスノートPCよりも高めで、自作デスクトップPCに接続したTP-Link Archer TX50UHとほぼ同じぐらいの感度になっておりました。
内蔵型のWi-Fiワイヤレスアンテナとしては非常に良いレベルの感度だと思われます。
Lenovo Vantageで設定が可能でアプリケーション上でも目立った機能向上が見られなかったネットワークブーストは、Wi-Fiの受信感度を強化するような機能かと思いましたが、どうやらそれは違ったらしい。
色々設定を変更してみたけど、謎のままの機能という事になりました。
電源管理やGPUのオーバークロックも可能なソフトウェアが便利
Lenovo LOQ 15IRH8対応の公式ソフトウェアLenovo Vantageは、ハードウェアのモニタリングやアップデートを行える他、コンピューターのパフォーマンスを最適化する機能を有しています。
内蔵バッテリーの急速充電や保全モードの適用、GPUのオーバークロックなどの内蔵ハードウェアの保守管理やシステム状態の表示などの、便利な機能が備えられています。
Lenovo LOQ 15IRH8 82XV006JJPの評価
本気で動画や写真編集をするのであれば、外部モニターを接続して使用する必要はありますが、元々ライブ配信専用PCとして考えていたので、申し分がない性能だと思っております。
ディスプレイの表示性能と内蔵バッテリーの持続時間に不満は残りますが、グラフィック性能や処理能力などの内蔵ハードウェアの総合性能に全振りをして、セールで13万円台はかなりお得ですね。









































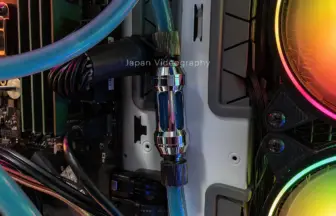
























この記事へのコメントはありません。